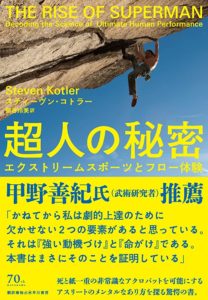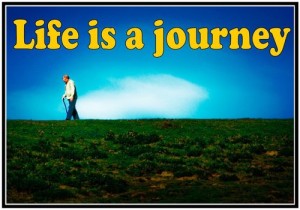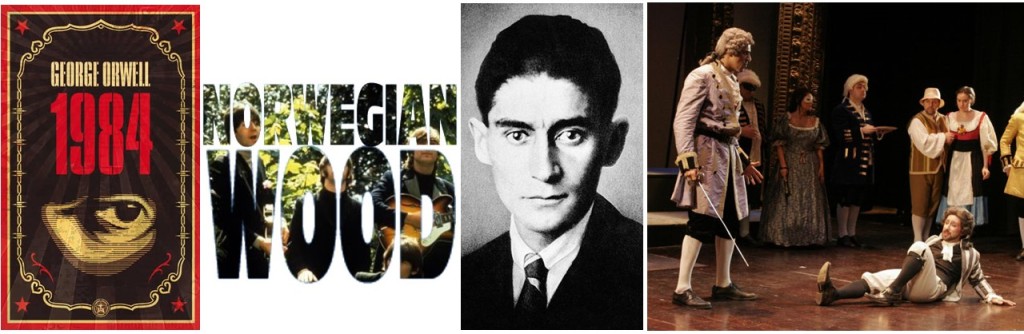→『本と映画とアート』トップに戻るときはコチラから
※後のものが上に来るように、書き足していっています。
『ZONE シリコンバレー流 科学的に自分を変える方法』(スティーヴン・コトラー、ジェイミー・ウィール)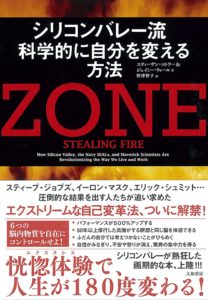
いや、、、こんなことははじめてです。
気がつかないまま、以前に読んだ本を再読しちゃうなんて(汗)
もちろん、意図的に本を再読をするということは、ときどきあるけれど。。。
まぁ、さすがに今回は途中で気がついたけれど、でもおもしろい本なので、けっきょくそのまま最後まで再読しちゃいました^^
読んだ本は、『ZONE シリコンバレー流 科学的に自分を変える方法』
原題は“Stealing Fire”。
人類のために、天界から火を盗んだプロメテウスの神話にちなんだものですね。
かつては「それ」に近づくことが許されていなかったし、いまでも多少危険な要素はあるけれど、もし「それ」を扱うことができるようになったら、根本的に人の生活を変える──プロメテウスが人類にもたらした「火」がそうであったように、「ゾーン」という体験はぼくたちにとってそのようなものになりうる……、そんな趣旨です。
邦題の「シリコンバレー流」とか「科学的」という言葉は、人の目を引くのには多少有効かもしれないけれど、この本の趣旨とかテイストに照らすなら、じっさいには「ちょっと違う感じ」です。。。
内容がいいからまぁ目をつぶるけど、ほんとうはアートとか狂気と隣接をした、人間という存在そのものをひっくり返しちゃうような領域に触れた本だと言ってもいいです。
★
ちなみに、共著であるこの本の一方の筆者であるスティーヴン・コトラーには『超人の秘密』という著作もあります。
「エクストリーム・スポーツ」──身体の安全が保障されていない危険なスポーツとゾーンの関係について書かれた本で、こちらも絶賛オススメです!
もちろん、今回取り上げる『ZONE シリコンバレー流 科学的に自分を変える方法』は、そのタイトルどおり「ゾーン」に関する本であることは間違いありません。
ゾーンとはチクセントミハイによって使いはじめられた言葉で、「フロー」「無我の境地」「忘却状態」などとも言われます。
本書では「ゾーンに入ると、集中力が極限まで高まり、ほかのいっさいのものが消え失せる。行動と意識が融合しはじめる。自分という感覚がなくなる。時間の感覚もまたしかり。心身両方のあらゆるパフォーマンスが、限界を超えて高まっていく」。
そして、「優秀な人とその他大勢とを分けるのは、やり抜く力でも、よりよい習慣でも、長時間の練習でもない。彼ら先駆者たちの話によれば、その意識状態になれるかどうかが鍵なのだ」とされます。
スポーツ選手がときどき「ゾーンに入る」って言い方をしているのを聞いたことのある人も多いでしょうし、ご自身でそのような経験を持つ方もいらっしゃるでしょう。
ぼくが瞑想教師をしているのも、この境地をみなさんと分かち合いたいというが最大の動機だと言えます。
(ぼく自身は、瞑想と関係あるのかないのか分からないまま、もともとゾーンに入るのは得意だったんだけど)
★
この本が、他のゾーン関連書籍から頭ひとつ抜けているのは、バラバラな個人が消えてひとつの集団として奇跡を起こす──「グループ・フロー」というテーマに触れている点です。
本書のはじめのほうで、アフガニスタンに潜入してアルカイダの重要人物を捕獲したネイビー・シールズの話とか、グーグル社がいかにして草創期の壁を乗り越えていったかという話が紹介されていて、それだけでぐいぐい引き込まれて、ページを読み進んじゃいます。
なんで、そういう話に引き込まれるのか?
もちろん話材としてもおもしろいし、文章も巧みなんだろうけれど、じつはその文章を読むことによって、読者であるぼくたちもまた「グループ・フロー」の影響を受けているんです。
そう、ゾーン(フロー)は「個人」という枠を超えるし、たぶん時間や空間の制約も超えるはずです。
この辺は、グローバル・アセンションにも通じる話かもしれません。
★
この本の趣旨をざっくりとご紹介をすると、ぼくたちがゾーンを得るためのひとつのカギが「エクスタシス(ハイになること)」。
ゾーン(フロー)の状態と、サイケデリックス(幻覚剤等)を使用しているときには同じ神経基質が使われているのだそうです。
すなわち、セロトニン、ドーパミン、ノルエピネフリン、エンドルフィン、アナンドアミド、オキシトシン──この6つです。
これらは単に「気持ちいい」だけでなく、社会的な結びつきを生むのに一役買っていると言います。
★
ということから、この本ではエクスタシスのうちの3つのカテゴリーが取り上げられます。
1.ZONEに入っている状態
2.瞑想的・神秘的な意識状態
3.サイケデリックな薬理学的状態
筆者たちは、上記のカテゴリーと対比して、違法なドラッグ、自己啓発プログラム、エレクトロニック・ダンス・ミュージック、SNS、ポルノ等に言及し、人がこれらにハマっているときにも、先に挙げた6つの神経伝達物質(とりわけドーパミン)が分泌されることを示し、人々は何とかして「自分を忘れて何かに没頭する時間を求めている」、、、けっきょくのところ「自分を解放すること」を望んでいるのだと言います。
──若干、論理の飛躍があるような気もしますが、直観的には納得です。
★
上記のなかには、ぼくがメインで取り組んでいる「瞑想」も入っています。
でも、じつは瞑想だけが他とはちょっと違うのです。
他のすべての方法は脳波がアルファ波、あるいはシータ波へと落ちることが、エクスタシスを得ることにつながるとされます。
ところが瞑想だけは脳波30Hz以上、すなわちガンマ波にあがることによって、変化が起きるのです。
このことは、本書にもチベット僧に対する調査として紹介されているし、ぼくが師事をしているボブ フィックスも常々語っていることだし、そしてぼく自身も(脳波の測定はしていないけれど)経験的、体感的に確信を持っている点です。
本書ではこの点について触れるのみで、そこから先の研究や考察がないのが残念ですが……。
★
それはともかく、エクスタシスの特徴を整理すると以下の4つの特徴が見て取れるとのことです。
ここはまた、瞑想も共通していますね。
1.セルフレスネス(自己からの解放)
つまらない「自我意識」から自由な状態になる。
2.タイムレスネス(時間からの解放)
「深い今」「永遠につづく現在」を生きている感覚になる
3.エフォートレスネス(楽々とこなせること)
通常の意欲の限界を超えてものごとに取り組むことができる。
自分の経験、ひいては人生そのものに本質的なよろこびと満足感を感じる。
4.リッチネス(豊かさ)
周囲で起きていることを、もっと多く、もっと正確に、知覚・処理できるようになる。
★
そして、筆者たちは「エクスタシスの4つの力」として、科学的にゾーンをつくりだす4つの方法を紹介しています。
そのうちのひとつが「心理学」による方法。
代表がスピリチュアル。
ほかにも、セックス、臨死体験、エクストリーム・スポーツといった経験に伴う、心理的な反応によってエクスタシスが生じる諸現象です。
2番目が「神経生物学」による方法。
わかりやすいところでいうと、ボディランゲージとか、顔の表情をつくるとか、ヨーガのように身体からアプローチをして、意識の状態に変化を起こす方法。
3番目は「薬理学」による方法。
ここでは合法的なドラッグの可能性に言及されています。
そして、4番目に「テクノロジー」による方法。
たとえば、安全にエクストリーム・スポーツを楽しめるマシン。
人々をトランス状態に導く音響システムやビジュアル・アート等々。
著者のうちのひとりジェイミー・ウィールは、もうひとりの著者スティーヴン・コトラーその他の協力を得て、上記を総合した「フロー道場」を運営しているそうです。
(ネットで見たら、ほんとうに‘Flow Dojo’って表記してありました^^)
★
あと、本書のなかで何度か「バーニングマン」というイベントについて紹介されています。
毎年8月末の1週間、ネバダ州の砂漠のど真ん中に、みんなで集まるというイベントです。
電気、ガス、上下水道、電話、ガソリンスタンド、テレビ・ラジオ・携帯電話の電波、売店、食堂もいっさい準備されていないところに、生存のために必要なものを、すべて自分の責任で事前に準備して参加しないといけない。
そして立ち去るときには、完全に元どおりにして撤収をする。
何かが提供されるのを求めていくのではなく、自分がみんなに対して何を提供できるかが求められる。
先に書いた草創期のグーグル社において、共同創業者のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンが、会社を託すべき人物としてエリック・シュミットを審査したのは、このイベントだったのです。
ほかにも数多くの経営者が参加して、たとえばイーロン・マスクはこのイベントでテスラの試作品を公開したり……。
この本の邦題に「シリコンバレー流」とあるのは、こうしたエピソードが元になっているものと思われるけれど。
ちなみに、ここでは貨幣経済や商行為は禁止されていて、見返りを求めない「贈り物経済」と「親切なこころ」が求められています。
(物々交換ですら推奨されていません)。
そんななかで、有名アーティストがパフォーマンスをしたり、著名人がレクチャーをしたり、その一方で無名の人たちがそのためのボランティアで会場設営をしたり……。
おもしろそうだから、いちど行ってみたいなと思うのですが、自分では何もせず、ただ「見にきた」という態度は恥ずべきことだ、とされているそうです。
ちなみに、日本版もあるそうですが……。
★
じっさいのところ、ゾーンについてはまだ解明されていないことも多く、みんなが試行錯誤中です。
この本も、著者たちの現時点における考えや取り組みを紹介したもので、まだ結論とか決定版というものではありません。
でも、何せ「プロメテウスの火」のようなものだから、取り扱いに注意が必要です。
注意すべきことのひとつが、国家(軍)と企業。
国家(軍)は他人や他国を支配下に置くために、企業は利益を独占するためにゾーンに関する知識と技術を自分たちだけのものにしようとします。
(というか、すでにそのために動いている実例も暴露されています)
著者たちは、それに対して「オープンソース化」を提言しています。
つまり、国家(軍)と企業のものにされるまえに、「みんなのもの」にしちゃうこと。
★
取扱注意は、国家(軍)と企業に対してだけではなく、自分自身に対しても必要です。
エクスタシスにはマイナス面もあるのです。
(快楽主義者のぼくにはとてもよくわかります^^;)
先にエクスタシスの特徴として挙げた4つのポイントに沿って言うなら──
1.セルフレスネス(自己からの解放)
しばしば、極度の「自我肥大」を招く。
「私には何でもできる」「私はキリストだ!」ってやつ。
著者たちは言います。「エクスタシーのあとにすべきは、自分自身の洗濯だ」
2.タイムレスネス(時間からの解放)
しばしば、時間感覚が歪みます。
1年でできるはずのないことをできると考え、10年あればできることをできるはずないと思ってしまう。
3.エフォートレスネス(楽々とこなせること)
至福中毒者(ブリス・ジャンキー)になる。
とてつもない困難に直面しているときこそ、たゆまぬ努力や辛抱強さが必要。
エフォートレスを手に入れるには、多大な努力が必要なのだ。
4.リッチネス(豊かさ)
フリー・ダイビングの教訓──「深く潜りすぎるな」。
エクストリーム・スポーツにおいては、そのようにして命を失った人たちがたくさんいる。
永遠に失ってしまう前に戻ってくること。
著者たちは、なかでも3と4は命取りになると言いますが、もしかしたらこのあたりは瞑想が他の方法と異なる点になるかもしれません。
ぼくが知るかぎり、瞑想者には3と4が命取りになったという人はいないんじゃないかと思います。
このことについては、後でまた書きます。
★
著者たちは、ゾーンに入る最良の方法は人によって違うとして、自分にとってどの方法がよいかを見極めるめやすとして、つぎの算式が紹介されています。
価値=時間×報酬/リスク
早い話が、エクストリームスポーツは瞬間的に、そして命を危険にさらす分だけ、得られるエクスタシスは大きい。
瞑想は安全だけど時間はかかるし、効果もマイルド。
サーフィンはその中間くらい。。。
先に瞑想者にとって、エクスタシスが命取りにつながったというケースを聞いたことがないというのは、そもそも瞑想はほとんどリスクのないマイルドなメソッドだから、というのが理由のひとつです。
★
でも、ぼくはここで、さらにもうひとつの意見を持っています。
「リバウンド」という観点からの意見です。
エクスタシスは得られれば得られるほど、それが抜けた後の反動が大きいです。そうすると、エクスタシスに浸っていないときの時間が虚しく感じられる。
その結果、つぎはもっと大きなエクスタシスを求める。
あるいは、いったんエクスタシスを得たら、そこから戻ってきたくなくなる。
結果的に、上記の3と4に陥りやすくなるわけです。
でも、瞑想は違うんです。
脳波30Hz以上=ガンマ波が定着したら、もう二度とそこからは意識がさがらないんです。
その状態で、ベータ波、アルファ波、シータ波、デルタ波といった他の脳波を統合していくのです。
具体的にいうと、意識のうちに瞑想状態を残したまま、日常生活に戻るんです。
仕事、人間関係、そして生活の雑事、睡眠、夢見……。
脳の相当領域で30Hz以上=ガンマ波を維持したまま、一部、ベータ波、アルファ波、シータ波、デルタ波による体験を重ねることによって、自分のなかの「残りの部分」を統合していくんです。
ここのところを、著者のふたりにお伝えしたいな。。。
(上から目線でごめんなさい)
★
ちなみに著者のふたりはリバウンドの問題については、「快感スケジュール」ということを提案しています。
それによると、複数のメニューを用意することだと言います。
たとえば、エクストリーム・スポーツ、生演奏、セックス、自己啓発ワークショップ、旅行……。
そして、それぞれのサイクルを決めて割り振る。
日に一度行うもの、週に一度行うもの、月に一度……、季節ごとに一度……、年に一度……。
まぁ、充実した人生を送るためのハック(ちょっとしたコツやアイディア)としては悪くないと思います。
★
ぼくは、たくさんの人に瞑想を教えて、誰にでも向いているとは言えないことは知っています。
瞑想が向いていない人には、他の方法でもいいから、ぜひゾーンという意識状態をマスターされるといいなと願っています。
でも、もし瞑想がそこそこ嫌いではないのなら、やっぱりメインは瞑想。
ポイントは脳波30Hz=ガンマ波なんです。
ぼくの感覚から言うと、エクストリーム・スポーツ等、瞑想以外にも脳波30Hz=ガンマ波を得られる手段はいくつかあると思います。
でも、そのほとんどはリスクがあるので「快感スケジュール」にしたがってインターバルが必要だし、たいていは歳をとるごとに体力等が低下するので、得られるエクスタシスも低減せざるを得ません。
ぼくにとって、どうしても忘れることができないのはジャック・マイヨールのことです。
フリー・ダイビングで数々の記録をつくっただけでなく、スピリチュアルにおいてもかなり高い境地に達したにもかかわらず、彼は最後にはうつ病で自死しちゃいました。
もし、彼にエクスタシスを「意識の残りの部分と統合する」術(すべ)があったなら……。
瞑想の道には、ちゃんとそこまで準備がされているのです。
◇ ◇ ◇
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
こちらに書くのはひさしぶりになります。
ほんとうはどうせ書くなら、ここはちょっとマニアックな映画で、「きっと、みんなあんまり知らないだろうけど、じつはちょっとすごい作品があってね……」みたいなコーナーにしたいんだけど、この作品はあまりにすごい、無視するわけにはいかない映画なので、絶賛で取り上げたいと思います。
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』──通称『エブエブ』^^
本年度のアカデミー賞主要8部門のうち、作品賞、監督賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞、脚本賞の6部門を制覇。
プラス編集賞も。
(現時点で、全世界興行収入1億ドル突破だそうだけれど、『すずめの戸締り』は134億円とのこと。
そうして考えてみると『すずめの戸締り』もすごいですね。。。)
でも、まぁ、ここでは『エブエブ』
内容的には、コインランドリー経営で生計を立てている中国系移民一家の話。
主人公の中年女性はADHD。
何をやっても途中で頭のなかが横道に逸れていっちゃって、いろんなことが取っ散らかっちゃてるんだけど、本人的には何をやってもうまくいかずにフラストレーション満載。
いまの最大の厄介ごとは、税務調査。
コトと成り行き次第では、経営するコインランドリーが差し押さえになっちゃうかもしれない。
並行して、頑固な古い家父長的なお父さんの介護。
タトゥーを入れて、レズビアンのガールフレンドを連れてくる反抗的な娘との葛藤。
やさしいけれど、スーパーマンとは程遠い夫とのあいだにかかえる離婚問題。
……
──って、ところから、突然マルチバースが展開(笑)
マルチバースとは、現代宇宙理論のひとつで、宇宙はひとつ(ユニバース)じゃなくて、たくさんある(マルチバース)という考え。
どれくらいたくさんあるかというと、あらゆる可能性の数だけある。
だから、いま自分がどんな状況にいようと、そこからありうるかぎり最高の状態にも、最低の状態にもジャンプすることができちゃう。
そんなところから、人生として最高の輝きを得ることも可能である一方、最低の邪悪さに呑み込まれることもありうる。
それは自分だけでなく、自分と関係する人それぞれについても言えること。
──ってなところから、登場人物同士のありとあらゆる可能性の組み合わせが錯綜して、ギャグとカンフーアクションとシュールとお下品ネタがちりばめられ、映画じたいがマルチバースと化していく……。
でも、テーマは一言でいえば「愛」。
それも、たとえば厄介な親、厄介な子ども、輝きを失った夫婦関係、同性愛、自分を攻撃してくる「敵たち」といったむずかしい関係性を、どのようにして「愛」へと変えていくか、というとてもとても難易度の高いチャレンジ。
なかでも重要なフレーズは、「自分のなかの怖れと葛藤が、争いを引き起こす」。
そう、「敵」は自分の外ではなく内にいるのだし、それはいつでも「愛」に変えることができる。
ラスボスは、葛藤を抱える娘のもつ可能性のひとつであるジョブ・トゥパキという闇の女王と、彼女がつくった大きなベーグル。
そのベーグルは、すべてを呑み込んでいくブラックホールになっている。
ここのところをどのように解釈するかがポイントのひとつになるけれど、ぼくは「愛を拒絶する虚無」と理解しました。
「ありとあらゆる可能性が同時にあるのなら、『何かを尊い』とする根拠なんかどこにもない」──ってことになるから、「クソつまらない、この世の中ですったもんだするのはやめて、ブラックホールの向こうにサヨウナラ」ってこと。
それは、別の場面で夫が、「何で、無数にある可能性の中から、わざわざこの世界を選んでやって来たのか、自分にも分らない」と言ったことにもつながります。
それに対する主人公の答えは(ぼくなりにちょっとアレンジして言うと)、「ここは、数ある可能性のなかから唯一、いま自分たちが選んだ場所なのだから、それを大切にしたい」ってことかな。
何も起こらない世界で、永遠に崖の上にとどまっている石であるよりは、あえてそこから転がり落ちてみる(おお、ローリングストーン!)
ぼくにとっては、これまで最高の映画は『マトリックス』であり、これを超える作品はあり得ないと思っていたけれど、『エブエブ』はあっさり超えちゃいました^^
でも、監督自身が「自分たちの『マトリックス』をつくりたいと思った」と言っているし、作品のなかでは「あ、この場面は、『マトリックス』のあのシーンを引用しているな」ってところがチョコチョコあって、『マトリックス』ファンにとっても楽しみがいのあるつくりになっています。
◇ ◇ ◇
『騎士団長殺し』(村上春樹)
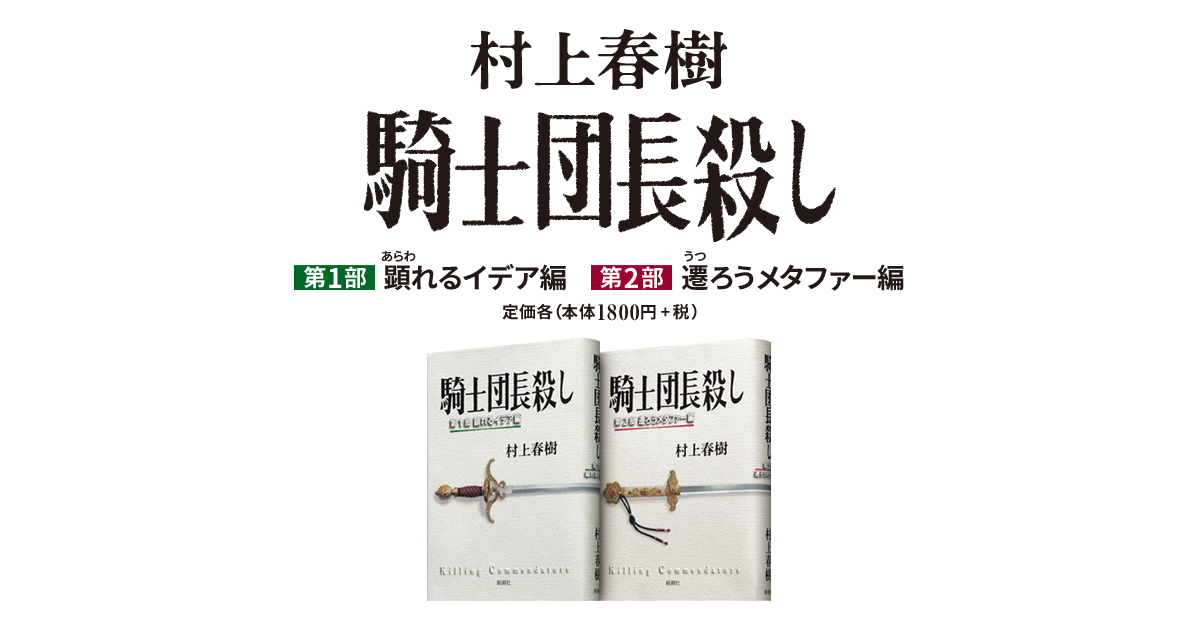
<意識のめざめ>と、小説の3分類
<意識のめざめ>のような探求をしていると、早晩「この世界はマーヤー(幻影)である」という、インドの古くからの教えに行きあたります。
そして、そこからふたつの課題が生まれます。
いかにこの世界(=マーヤー)から自由になるか?
そして、自由になったからといって、消えてなくなるわけではないこの世界(=マーヤー)といかに関わっていくか?
★
じつは、小説や映画などのジャンルにおいても、これと並行した取り組みが行われているのです。
そもそも、小説とか映画には大きくいって3つある──と、ぼくは勝手に思っています。
(1)世界の中で展開する話
(2)世界の中に収まりきらない話
(3)世界を乗り超えていく話
「(1)世界の中で展開する話」というのは、みなさんにとっていちばんお馴染みの作品群といっていいでしょう。
登場人物たちが何かをめざし、ときにうまくいき、ときにうまくいかない……。
その「何か」とは、恋愛であったり、戦争であったり、犯罪であったり、ビジネスであったりするけれど。
読者や観客もまた、あたかも登場人物になり切ったかのように同一化をし、物語にのめりこんで、その「何か」を追体験する。
そのあいだ、登場人物たちは(そして、読者や観客も)その「何か」に夢中になっていて、それが虚構(フィクション)であるということを忘れます。
こうした作品は、おおむね現在の基準では「芸術」ではなく「娯楽」として扱われます。
これらは「この世界はマーヤー(幻影)である」だなんてことは考えたこともない、という状態に対応していると言えるでしょう。
もちろんアリストテレスの言うとおり、読者や観客はそうした作品をとおして、カタルシスを感じることができるわけだから、それはそれで価値があります。
(2)世界の中に収まりきらない話
けれども、ときおり「<自分>を取り巻く<世界>」に違和感を感じる人たち、というのがいるのです。
あるいは「この<世界>にいる<自分>」に違和感を感じるという人も。
ある意味で「哲学」というのはその違和感を埋めようとしてつくられものだから、たぶんずっと昔からそのような人たちはいたのだろうけれど、社会のなかで目につくようになったのは、いわゆる「近代」以降のことだと思われます。
かつては堅固であった宗教がほころびを見せはじめ、それまで確かだとされていた「世界観」が揺らいできたせいです。
そしてそれに連動して、確かな「生き方」もまた揺らいできたから。
いったんそのような違和感に掴まってしまうと、かつてはあれほどのめりこんでいた「何か」が、急速に色褪せていく。
場合によると、嫌悪すら感じるようになる。
それまで優等生で、親や先生の言うことをよく聞き、学校の成績も優秀だったのが、思春期になったあたりから「親や先生の言うことは嘘くさい」と感じ、「勉強なんかして、それが何の役に立つのか」と思うようになる──まぁ、そんなような感覚に似ているかもしれません。
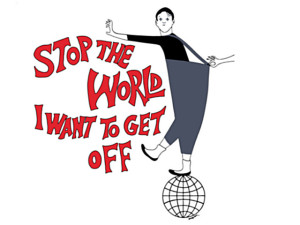
そんな<自分>と<世界>の関係を描く──ブンガクに携わる人たちのあいだでは、そういう作品のことを、狭い意味での「小説」と呼びます。
そのような作品はたいてい「(2)世界の中に収まりきらない話」という形をとり、もちろん小説だけでなく映画にもそういうのは少なからずあります。
そうした作品は、しばしば「娯楽」としてはおもしろくないけれど、「芸術」としては価値があるとみなされます。
「<自分>を取り巻く<世界>」に違和感を感じたり、「この<世界>にいる<自分>」に違和感を感じる人たちにとっては、ニコニコと娯楽を楽しむような気分になんてなれないから。
これらは「この世界はマーヤー(幻影)である」ということに気がついた状態に対応していると言えるでしょう。
ただし、マーヤー(幻影)だからといって、それが消えるわけではなく、そのマーヤー(幻影)に悩まされ、いったいどうしたらよいのか途方に暮れているという状態です。
★
村上春樹さんもまた、「いまの世の中には、もうひとつ馴染めない」という人たちに関する作品を書いてきた作家のひとりです。
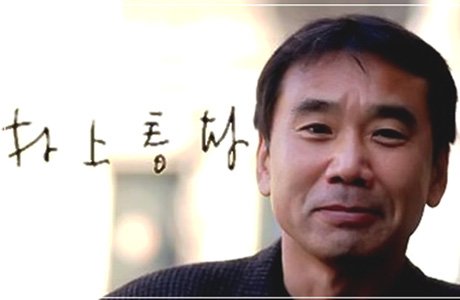
村上さんがデビュー当初描いたのは──、世間からは距離を取って、ささやかだけれど、自分ひとりがそこそこ心地のよいライフスタイルをもって静かに暮らす……、そんな人たちの姿でした。
おおむねどの作品においても、主人公は基本的に会社勤めも、近所づきあいも、結婚もせず、自分ひとりが何とかやっていけるくらいのフリーランスの仕事と、広くはないけれど小ぎれいな住まいを見つけて、有名になることにも成功することにもお金儲けにも興味はなく、できるだけ他人とは厄介ごとを起こさず、特別にリッチというわけではないけれど、まぁまぁ清潔で趣味のいい洋服と音楽と小説をほどよく嗜み、器用にパスタやサンドイッチをつくり、ジムには行かないけれどジョギングをし、男と女のドロドロにはまることなく、手間のかからない(でも風俗嬢ではない)女の子とときたまセックスをする……。
いまとなってはくわしい内容は忘れちゃったけれど、いわゆる初期三部作はどれもそんなようなイメージです。
ぼくはけっこう好きでした^^
村上さんは、ぼくが高校生のころデビューをされたのですが、当時の世の中にはまだ「世の中に馴染めないからといって、若隠居みたいな生活に逃げてどうする。きちんと社会にぶつかっていって、世の中を変えるか、せめて揺さぶりをかけてみろ! じゃなければ自分が変わるか、それができないなら玉砕だ!」みたいな思想が残っていて、芥川賞を取れなかった背景のひとつも、そのあたりにあったように思います。
なかには『羊をめぐる冒険』という作品もあって、初期のころの作品は基本的にリアリズム路線だったけれど、そこにひょいと現実にはあり得ない何かが割り込んでくる……、最近の村上作品の嚆矢ともいえる作品で、じつはぼくはこれが一番好きでした。
★
でも、ぼくは『ノルウェイの森』以降、村上さんの新作を追うのをやめました。
『ノルウェイの森』は売れに売れて、村上さんが「国民的作家」となった記念碑的作品ですが、ぼくとしてはこの作品だけは好きになれなかったのです。
それまでの村上さんの作品は、おおむね「<自分>を取り巻く<世界>」に違和感を感じている主人公が、そんな<世界>に煩わされずに生きていくことのできる隙間をみつけて、そこで<世界>に対して戦うのでもなく、屈するのでもなく、だいじに<自分>を育んでいる……って感じで、そこが彼の作品の美点でした。
それに対して『ノルウェイの森』には、「<自分>を取り巻く<世界>」や「この<世界>にいる<自分>」に違和感を感じている人たちがたくさん登場して、その多くがけっきょくは自殺をするか、精神を病むか、あるいは消息を絶ってしまいます。
それを横目に、主人公の「僕」は最後まで自殺もせず、精神の病いも得ず、消息も絶たず、最後にはとってつけたような前向きな終わり方をしちゃう……。
死んだり、狂ったり、消えていった人たちに対するオトシマエがついてないじゃないか──少なくともぼくにはそう感じました。
つまり、村上さん自身が感じていたはずの「<自分>を取り巻く<世界>」や「この<世界>にいる<自分>」に対する違和感に対して、どういう決着をつけたのか?
──ぼくにとって共感できるポイントが見つけられなかったのです。
まぁ、いまから思えば、けっきょくはオトシマエも決着もあり得ない、それでも前を向いて生きていくしかない、ってことなのかもしれないけれど……。
そして、この作品は村上さんにとって、自分ひとりが無難に生きていける隙間から出て、他者と痛みを共有しながら生きていくという道を選んだ、第一歩ともいうべき作品だったのだろうけれど……。
「(3)世界を乗り超えていく話」に挑む
そんなこんなでそれ以来、ぼくは村上さんの熱心なフォロワーではなくなりました。
けれど、ずいぶん後になってから『海辺のカフカ』とか読んで、村上さんが進化しているのには舌を巻いたものです。
基本的にリアリズムの作家だったのに、作中唐突に<世界>に穴を開けちゃう。
もちろんそれまでも何作かは、リアリズムを逸脱した作品も書いていました。
でも『羊をめぐる冒険』はそもそもそういうファンタジーだし、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』はそういう「小説的構造」だったから、たとえそれが現実にはあり得ない出来事だったとしても、作品世界のなかでは物語はふつうに進行します。
でも、たとえば『海辺のカフカ』はちょっと違うんです。
読んでいて、途中で「えっ?」となる。
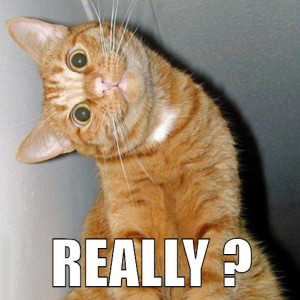
登場人物にとって<世界>が破れるだけでなく、読者にとっても<世界>が破れる。
ってか、「小説」じたいが破れる。
「まじっすか?」、みたいな。
これは作者にとっても勇気がいることのはずです。
ヘタしたら作品が壊れかねないから。
村上さんは、今回の『騎士団長殺し』のなかで、セロニアス・モンクについて、「彼にしか出せない和音」ということを書いているけれど、村上さん自身もまた小説においてそれを紡ごうと試みているかのようです。
「小説」が破れるということについて、もう少していねいに説明をしておきましょう。
ふつう作家さんは、読者にとって、なるべく無理なく自然にストーリーを追えるような作品を書こうとします。
というのは、そもそも小説は虚構(フィクション)だから。
虚構(フィクション)なんだけど、読者にはそのことを忘れて作品にのめり込んでほしい──だから作家さんは、なるべく無理なく自然にストーリーを追えるように書こうとするわけです。
にもかかわらず、ある種の作家さんたちは、わざとその「お約束」をぶち壊しちゃうんです。
なぜか?
それは、<世界>や<自分>もまた、ある種の虚構(フィクション)じゃないかと疑っているからです。
<世界>や<自分>を疑っている状態で、<小説>が虚構(フィクション)だということを忘れたふりなんかできないんです。
だから、現代の小説においてはしばしば、つぎのような対応関係が探求されることになります。
(A)ぼくたちが現実世界において感じている「<自分>を取り巻く<世界>」や「この<世界>にいる<自分>」に対する違和感に対して、どのように取り組んでいくか?
(B)小説の登場人物が感じているであろう「<自分>を取り巻く<世界>」や「この<世界>にいる<自分>」に対する違和感とそれに対する取り組みを、どのように受け止めるか?
(C)「<小説>という虚構の<世界>」について、その虚構を書く作業、読む作業をどのように進めていくか?
作中の登場人物が「こんなに生きづらい世界と、どうやって関わっていったらいいのか」という問題に取り組むのと並行して、作者や読者は「<小説>という代物と、どうやって関わったらいいのか」ということを手探りしながら、作品が進んでいく……。
単にストーリーが展開して、そのなかで主人公があれこれの経験をするだけでなく、作者や読者にとって、そもそも<小説>が作品として成り立つかどうかということじたいが問題となるのです。
ぼくたちはいかにこの世界(マーヤー)から自由になるか?
そのうえで、いかにこの世界(マーヤー)と関わっていくか?
そのことと、いかに小説を書き、そして読むのか?、ということがリンクしてくるわけです。
村上さんは、たぶん『海辺のカフカ』あたりから登場人物のあり方だけでなく、小説作品のあり方についても、「(3)世界を乗り超えていく話」に挑む作家さんになっていたように思います。
★
さて、むずかしいのはここからです。
破れた後、どうするか?
登場人物にとって、世界が破れた後。
そして、小説作品が破れた後。
──そこから、どうするか?
「実験小説」の類には、破れちゃってそれでお終い……みたいな作品も少なくありませんが、そんなものを読まされる側はたまったものではありません。
破れた後、あたらしい「どこか」に辿り着けるかどうか。
しかも、破綻する前よりも、少しは何かよきものが多いであろう「どこか」に。
──それがちゃんと説得力のある形で示されるかどうか。
『ノルウェイの森』においては、小説としての破れはありませんでした。
村上さんの初期のころからお得意の端正なリアリズム小説です。
でも、「<自分>を取り巻く<世界>」や「この<世界>にいる<自分>」に違和感を感じている人たちが自殺をしたり、精神を病んだり、消息を絶ってしまう……。
登場人物たちにとっては破れがあったわけです。
そして、ただ主人公だけが最後になって、唐突に前を向いて生きることを決意して作品が終わる。
ぼくは、そこのところに説得力を感じられなかったわけです。
ただ、単に破れから目を逸らせているだけなんじゃないか……。
ぼくは、基本的に村上さんが好きです。
破れた先に、なお光を見つけようとしつづけてきたから。
でも、村上さんのみならず、いまを生きるほとんどの人は、この世界とは別のどこかにパラダイスがあることを信じるほど無邪気にはなれません。
話はちょいと逸れるけれど、ぼくが「スピリチュアル」と言うとき、気をつけているのもこの点です。
「スピリチュアル」は別にパラダイスじゃあない。

破れの向こうに<世界>があったとしても、そこもまたここと同様に欠陥がいっぱいで、問題の多い世界なんだろうけれど、でもそれが分かったうえで、<その世界>に触れることをめざしてみる。
そして、そのことは<世界>という言葉を<他者>という言葉に置き換えても同じではないか?
自分と同様、どこかに完全な人がいるわけではない。
けれども、そんな不完全な人間同士だけれど、何かの縁で触れ合うことによって、ひとりで生きていたんじゃできない経験をして、そしてまた前を向いて生きていくために必要な光と色どりをお互いに与え合うことができるかもしれない。
──そのような希望を示唆したのが、『1Q84』という作品だったのです。
<天吾の世界>と<青豆の世界>。
そして、天吾と青豆。
お互いの破れのむこうに向けて、それぞれが手を伸ばしあう。
その手と手が触れあって、そこから何かが始まることを期待したい──というところでこの作品は終わっています。
『騎士団長殺し』の構成とタイトル
長い前置きになりましたが、『騎士団長殺し』は以上のような背景と経緯をもって書かれた作品です。
一応、誤解のないようにお断りしておきますが、ぼくは村上さんが好きだけれど、ぼく自身が<意識のめざめ>で提唱していることと、今回の作品は必ずしも趣旨を同じくするものではありません。
どちらかというと、「いかにこの世界(=マーヤー)から自由になるか?」という点では別の道をめざし、「そのうえで、いかにこの世界(マーヤー)と関わっていくか?」という点では大きなヒントを感じています。
でも、まぁ、順番に話を進めましょう。
★
この作品は全2巻で第1部が「顕れるイデア編」、
第2部が「遷ろうメタファー編」。
小説というより、まるで論文のように解りやすい構成とタイトルです。
基本的にぼくにとってこの作品は☆☆☆☆☆(星5つ!)なんだけど、あえていうと解りやすすぎるのが難かもしれません。
解りやすすぎるというのは、この作品の登場人物でいうなら免色さんのようになりかねない、ということ。
あまりに計算が立ちすぎると、後に述べる「シェキナー」を殺してしまいかねないのです。
そこのところ、村上さんは作中で
「いまはまだ絵を完成させてはいけない」とか
「環を閉じようとはしたけれど、まだ完全には閉じていない」
といった表現をして、アーティストとして当然心得ていらっしゃるだろうことは見て取れます。
でもやはり、今回はちょっと理が勝っているかな。。。
西洋人の読者(こういう言い方はしたくないけれど、たとえばノーベル賞選考委員とか)を少し意識しているのかもしれません。

さて、構成とタイトルに話をもどすと、要するにこの作品のみならず、そもそも小説も、そしてこの世界も、イデアとメタファーで成り立っている──というのが、この作品の骨子となっています。
イデアというのは理念。
たとえば、「○○は××である」。
具体的に言うと、
「他人には親切にすべきである」
「生きていくためにはお金が必要である」
「赤信号では止まるべきである」
……
子どもが親を困らせるように、「なぜそうなの?」と問いつづけていくうちに、ほんとうは根拠は定かでないにもかかわらず、無条件にそう言い切っちゃう。
この世の中は、たくさんのイデア=理念で成り立っています。
みんなのあいだでそうことを共有できなければ、世の中は成り立ちません。
薄っぺらい言い方をするなら、それは「お約束」ということであり、それらしい言い方でいえば「契約」ということになっていったりします。
世の中と同様に、小説もまたイデアがなければ成り立たないのです。
まず第一に、作者と読者が共有できる「言葉」がないと作品が書けないし、登場人物とか、舞台背景とか、事件とか……、ほんとうは存在しないことについて、とりあえずそれが「ある」という想像を共有すること──そこには作者と読者の無言の「お約束」があるわけです。
そう、「○○は××である」。
あるところまではイデアが必要です。
でも、あるところまでいったら逆にそれがじゃまになる。
生々しい「現実」とか、あるいは「真実」と呼ばれている何ものかは、硬直した「お約束」の範疇には収まらないから。
生々しい「現実」や「真実」と呼ばれている何ものかと真剣に取り組んでいると、しばしば「お約束」=すなわち「イデア」が壁として行く手をはばむ……、なんてことが起こってきます。
たとえば、道路の向こうで愛する人が危うい目にあっているとき、赤信号が青になるのを待つのか?
生々しい「現実」や「真実」を前にしたとき、もしかしたら人は、それまで自分を支え、導いてくれた「お約束」=「イデア」と決別をしなくてはならないかもしれません。
先ほど書いたことと対応させるなら、それが「破れ」に相当します。
登場人物は、作品世界の中で「破れ」を体験するでしょうし、もしかしたら作品自体が<小説>として「破れ」を起こすかもしれません。
精神分析学では、それを象徴的に「父殺し」と言います。
あまりにわかりやすく図式的になってしまうので、村上さん自身がこの作品の中で、「まっさきに精神分析学的解釈をされるかもしれないけれど、でもやっぱりそうなんだもん」という趣旨のエピソードを差し挟まざるを得ないくらいに……。
いちおう、精神分析学についてくわしくない方のために少し補足をしておくと──。
赤ちゃんは、まっさらの状態で生まれてくると信じられています。
よくいえば無垢で、純粋で、活力に満ちて自由。
でも、好き勝手で、しばしばうるさくて、汚く、危なっかしい。
社会の中で、きちんとした人間として生きていくためには、しつけが必要です。
そのための規範を示すのが、多くの場合、父親の役割となります。
精神分析学では、象徴的にそれを「父」と呼びます。
先ほどの話とつなげるのであれば、「父」がイデアの担い手とされるわけです。。
子どもが成長するためには、「父」が必要です。
でも、成長するにつれて、しばしばそれと衝突をすることになります。
自分が本来もっていたはずの無垢、純粋、活力、自由を制約するものとして。
やがて、子どもは父にしつけられた制約を乗り越えて、自分なりのしかたで社会規範と向き合うことになるでしょう。
そのことを「父殺し」と言うわけです。
それまで自分を支え、導いてくれてきた規範をいったん破棄する成長過程です。
★
「父殺し」、すなわち「お約束」=「イデア」と決別をしたとして、さて、そこからどうしたらいいか?
とりあえず、立ちはだかっていた壁の向こうに抜け出る穴を見つけて潜り込むのもひとつの方法です。
そこしか進む道が見つからないのであれば仕方ありません。
穴の中がどうなっているのか?
そこから抜け出ることができるのか?
どうやって?
抜け出たら、その後どうなる?
……
それは分かりません。
もはや、自分を支え、導いてくれた「お約束」=「イデア」は存在しないのだから。
そんななかで、いささか心もとないけれど、もしかしたら手がかりになるかもしれないのがメタファーです。
メタファーというのは隠喩。
隠喩というのは、比喩の一種なんだけど、それが比喩だと明示していない形式のものです。
たとえば、「人生は旅のようなものである」というのは直喩。
それが「人生は旅だ」となると隠喩になります。
つまり、イデアにおいて「○○は××である」というとき、○○=××であることに有無を言わせません。
でも、メタファーにおいて「○○は××である」というとき、○○≠××であることが大前提です。
そこから、○○と××のつながりを感じ取るところに妙があるわけです。
作家の立場であり、そして隠喩の天才である村上さんに即していうなら、○○と××のつながりを創造していくといってもよいでしょう。
★
さて、父を殺したその先は……。
ある意味でネタバレになっちゃうけど、でもけっきょくははじめから解っていることなので書いちゃいます。
穴の中では生きていけないから、そこで死ななければ、いずれどこかに出ることになります。
つまり、○○≠××を大前提にして、「○○は××である」というメタファーを発見するわけです。
けれども、壁の向こうに広がっているのも、けっきょくはまたひとつの「世界」にすぎません。
これまでいた「世界」とはビミョーに違うかもしれません。
でも、そこでまた人は生きていくわけです。
日々が経過していくうちに、そこでまたすべてはおなじみの景色の中に溶け込んでいくことでしょう。
もしかしたら、はじめはメタファーだったはずの「○○は××である」が、いつのまにか強固なイデアになっていくことだってありえます。
主人公の「私」は父を殺して古い世界を後にしたけれど、けっきょくは新しい世界で、いずれは自分自身がつぎなる父になっていくことを引き受けることになります。
賛否の分かれるところかもしれないけれど、ここが村上さんにとってこれまでの作品と大きく違うところです。
これまでの村上さんの作品は、一貫して父になることを忌避しつづけてきました。
つまり規範を守り、子どもにそれを押しつけるという役割は担当しない、というのがかつての彼の選択でした。
何人かの評論家が、今回の作品は、村上さんにとってお馴染みの道具立てをフル装備して目先だけ変えたお約束のエンタテイメント──みたいな書き方をしているけれど、いったいどこに目をつけているんだ、と言いたいです。
デタッチメントが代名詞だった村上さんが父となることを引き受けるって、ほとんど改宗に近いことなのに。
さらに言うなら、父になることを引き受けるということは、いつでも「父殺し」の対象となることをも引き受けるということです。
騎士団長が身をもって示してくれたのは、そのことでした。
★
けっきょくのところ、希望をもって生きようとするなら、自分自身が誰かの希望に関与する必要があるということ。
自分のためだけでなく、誰かのために生きるという覚悟が必要だということ。
自分の世界を向こう側に押し開くことによって、別の誰かの世界との接点を見つけること。
──ここまでが『1Q84』で辿り着いた地点でした。
天吾と青豆。
そして、<天吾の世界>と<青豆の世界>。
そのいずれもが希望を求めて、破れ目の向こうに手を差し延べる……。
イデアというのは「○○は××である」ということでした。
だから、○○=××にあてはまらないものは、切り捨てられてしまいます。
もしかしたら切り捨てたものの中に、もともとはもっていたはずの無垢、純粋、活力、自由が含まれていたかもしれません。
人は大人になるために、つまり<自分>を形づくって<世界>に参加するために、しばしばそれらを手放してしまいます。
そして、もし自分が何か大切なものを切り捨ててしまっていたとするなら、それはもはや<自分>の中を探すことによっては、見つけ出すことはできないかもしれません。
じゃあ、どうしたらいいのか?
答えは<自分>の中にはない。
だとしたら、<自分>にとっての希望の鍵は、<自分>の外にあるということになります。
<自分>を救うことができるのは、<自分>ではなく<他者>。
さらに言うなら、<自分>にできるのは<自分>を救うことではなく、<他者>のために生きること──。
希望をもって生きようとするなら、自分自身が誰かの希望に関与する必要があるということ。
自分のためだけでなく、誰かのために生きるという覚悟が必要だということ。
自分の世界を向こう側に押し開くことによって、別の誰かの世界との接点を見つけること。
──というのは、そういうことなんです。
そして、今回の『騎士団長殺し』では、そのひとつの形として、父になることを引き受けるという決断に至ったわけです。
さらにいうなら、『騎士団長殺し』の「私」は、生物学的には自分ではない誰か別の男性の子どもの父になろうとしています。
それはイデアだけど、同時にメタファーでもあるということです。
○○≠××ということを分かったうえで、なおかつ○○=××であることを引き受けるということ。
これが唯一の解ではないと思うけれど、それでもここまで誠実に世界と人生と小説に取り組まれた村上さんに敬意を表したいと思います。
シェキナーの現身(うつしみ)
希望をもって生きようとするなら、自分自身が誰かの希望に関与する必要がある──そのひとつの形が、「父になること」だと言いました。
じつは、それ以外の形もないわけではありません。
村上作品に登場する女性たちが、その見本を示してくれています。
以前にある評論家が、村上さんの作品に登場する女性たちは、おおむね「都合のいい女」ばかりだといって批判をしていました。
主人公(すべて男性ですが)の側では大した苦労も葛藤もなく、女性のほうから好きになったり、身体を許してくれて、そして本来主人公が自分で乗り越えるべき課題を、代わりに引き受けてくれる……。
まぁ、典型的には『ノルウェイの森』の直子がそうだったりして、それが露骨だったからぼくもこの作品が好きになれなかったわけだけれど。
ただ、ぼくはその評論家さんのように、それで村上さんを非難しようとは思いません。
先に書いたように、村上さんの側に立って「でもやっぱりそうなんだもん」と思うから。
ぼくが思うに、その評論家さんの方こそ「そこのところ」を感得なさっていない。
「そこのところ」というのは、ユダヤの教えでいうところの「シェキナー」のこと。
つまり、「神的女性原理」。
女性原理というのは形にならない(形を与えるのは男性原理)から、説明することはむずかしいんです。
ちなみに、シェキナーという言葉のもともとの意味は「住居」。
エジプト神話を知っている人であれば、「ヌート」=空間の女神のことを思い出してみてください。
彼女は「何者か」ではなく、「何者かの存在が可能となる場所」です。
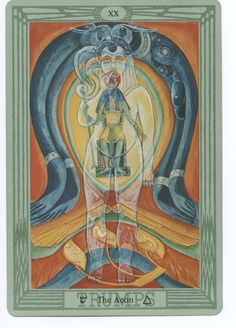
「何者か」をつくる創造主はある意味で男性原理なんだけど、そもそもそれを可能にしているのが女性原理であるシェキナー。
うーーーん、分かるかな?
★
シェキナーはそれじたいは形にならず、形あるものを成り立たせている「なにものか」だから、直接的にはぼくたちの目には見えません。
ちょうど、村上さんの今回の作品でいうなら、免色さんの家の開かずの間のクローゼットのなかに吊るされたいまは亡きまりえの母親の洋服のように……。
ぼくたちを、その「なにものか」に結びつけてくれるのが、アレイスター・クロウリーが「ベイバロン」といい、柳田國男が「妹(いも)の力」といった存在です。
「ベイバロン」とは、聖書『黙示録』のなかでは「大淫婦バビロン」として貶められた大いなる存在。
誰も拒絶しない聖なる娼婦として、この世のいっさいの穢れを引き受け、みんなに生命を与えます。
ときに、みずからが神殿の入り口となり、ときに、緋色の女としてタントラ行者にとってのヨギニーの役割を引き受け、ときに、大地の女(グレートマザー)となる。
もう一方「妹(いも)の力」とは、古代日本より伝わる女性信仰のこと。
妹(いも)というのは、いわゆる妹(いもうと)のみならず、親族、恋人その他、近しい女性のことを、昔はすべてそう言ったみたいです。
古来より日本では、男性は「形」を担当するけれど、その「形」を成り立たせる「力」は女性の霊力によると信じられてきました。
だから、女性からそれを与えてもらわない限り男は生きていけないし、この社会も成り立たない。
ときとして、そのために女性はみずからを犠牲にさえする……。
村上さんは、ひとりの男性として、そして芸術家として、直観的にそのことを感じて、表現してきたのです。
でもやっぱり、『ノルウェイの森』ぐらいまでは「都合のいい女」くらいの書き方しかできていなかったし、『1Q84』でも『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』でも、まだ「そこのところに」届いてはいなかったように思います。
それが、とうとう今回の『騎士団長殺し』ではしっかりと「届いた」──ぼくはそのように感じました。
この作品に出てくる何人かの女性たちは、それぞれがきちんと魅力と説得力をもちながらベイバロン、あるいは妹(いも)としての役割を果たしています。
ということで、自分自身が誰かの希望に関与するためのひとつの形が「父になること」(当然、いずれは「父殺し」の対象となること)。
別の形のうちのひとつはシェキナーの現身(うつしみ)として、ベイバロン、あるいは妹(いも)になること……、ぼくはそんなふうに思っています。
「現実」を作っているのは<自分>じゃないから
長い文章になったけれど、最後は脱線気味に締めさせてください。
『騎士団長殺し』を読み終えてまもなく、森田健さんの文章に触れたのが脱線のきっかけです。
森田健さんも村上春樹さんと同じく、第1作からずっとお仕事を拝見している方のひとりです。
森田さんは「運」ということについて探求しているけれど、彼の出している会報誌『不思議の友』につぎのようなことが書いてありました。
──「人が何かを引き寄せる」のではなく、「何かに引き寄せられる」のだと。
たとえば、森田さんは六爻占術というのを紹介しているんだけど、彼によると、貧乏人が金持ちになりたいと思ってコインを振っても貧乏な卦しか出ないし、そのとおりの現実しか引き寄せられない、と。
ただ、その人の金運の場がそこに反映されるだけ。
その場は自分で作り替えることができるかというと、残念ながらそれはできない。
なぜなら、人が場を作っているのではなく、場が人を作っているのだから。
自分の人生を作っているのは「場」である。
もしそう言いたければ「神」とか「宇宙」という言葉を使ってもいいけれど。
間違っても、その逆じゃあない。
──スピリチュアルに親しんでいる人からすれば、特別に目新しい話ではないだろうし、それを「社会」とか「構造」という言葉に置き換えれば、人文科学の世界でもよく言われてきたことです。
にもかかわらず、人はつい「自分」が「現実」を作っていると思い込んじゃう。
ここまで書いてきた言い方にもどるなら、誰しもがもともとは無限の可能性をもっていたはずなのに、大人になる過程において、<父>=イデアの鋳型に嵌められて形づくられた、一時的な現象──それが<私>なんです。
イデアが<私>を形づくったのであり、<私>がイデアを作ったのではない。
だから、<私>にはイデアを変えることはできない。
それは、自分が座っている椅子を持ち上げようとするようなものだから。
ところが森田さんによると、自分で「自分の場」を作り替えることはできないけれど、他の人の場には関与できると言います。
つまり、自分が座っている椅子を持ち上げることはできないけれど、人が座っている椅子を持ち上げることならできるかもしれない、というわけです。
★
村上春樹さんの『騎士団長殺し』に話を戻します。
先に、ぼくは
希望をもって生きようとするなら、
自分自身が誰かの希望に関与する必要があるということ。
自分のためだけでなく、誰かのために生きるという
覚悟が必要だということ。
自分の世界を向こう側に押し開くことによって、
別の誰かの世界との接点を見つけること。
──そのひとつの形が「父になること」を引き受けるということであり、もうひとつ別の形が「シェキナーの現身(うつしみ)」となることだと書きました。
『騎士団長殺し』が、これまでの作品から大きく一歩前に踏み出したと感じさせられるのは、「相対的で流動的な関係性」に目覚めた点にあると思います。
たとえば、「父になることを引き受ける」あるいは「父殺し」ということについて言うなら──
主人公の「私」にとって、実の父との関係は希薄です。
ある意味で「私」の人生の希薄さは、実の父との関係の希薄さに起因しているといってもよいかもしれません。
だから「私」は若いころは抽象画に惹かれ、でもけっきょくは社会に受け入れられるほどのレベルに達することはできませんでした。
この物語は、「私」が抽象画から離れて、食べるために具体的な人物を描くという作業をはじめるところから始まっています。
そう、具体的な生身の人間と向き合っていくこと。
けれども、まだその段階ではその仕事を「本来の職業」として腹をくくっていなかったから、けっきょくは義理の父にも認められることはありませんでした。
離婚した「私」は、彼を庇護してくれるような父親をもっていなかったので、友人雨田政彦の世話になります。
雨田は「私」とは逆に、あまりに偉大すぎる父の息子であることに苦しんだけれど、父親とは別の道を行くことによって、それなりに成功した人生を歩んでいます。
そんな雨田の父が描いた絵が『騎士団長殺し』であり、その絵のテーマが「父殺し」だったのです。
そして、その絵から姿を借りて、小説世界に出てきたイデアの主=騎士団長を実際に(?)殺すのは主人公の「私」です。
もちろん、騎士団長は「私」の生物学上の父ではないです。
もっと言うなら、メタファーとしての「父」ですらないかもしれません。
その刺殺は、友人雨田の包丁を使って、雨田の父の目前で行われ、そしてそれからほどなく雨田の父は息を引き取った──つまりメタファーということをいうのであれば、「私」が殺したのは、雨田の「父」であり、雨田の父にとっての「父」だったと言えるでしょう。
そして、その「私」がこちら側の世界に戻ってくるとき、穴の上から手を差し伸べてくれたのは免色さんでした。
何も持たない自分を、生きていく場に引き上げてくれる──ある意味で「父」とはただそのためだけにいるようなものです。
つまり、免色さんはその瞬間に、象徴的に「私」の「父」の役割を果たしてくれたとも言えます。
その免色さんはというと、実の娘かもしれない秋川まりえの「父」になることは諦めています。
それに対応するかのように、「私」は生物学的にはつながっていない子の「父」となることを引き受けようとするわけです……。
★
ちなみに、主人公の「私」にとって騎士団長殺しは、直接には「父殺し」を意味してはいないでしょう。
ストーリー上の動機としては、「私」はあくまでも秋川まりえを救うために、騎士団長を殺して穴に入り込んだのです。
まりえはどことなく、大人になる前に死んでしまった妹と重なる部分があります。
「大人になる前に死んでしまった妹」というのは、ある意味で主人公の「私」が大人になるために犠牲にしてしまったかもしれない諸々のメタファーだとも言えます。
表面的なストーリー上では、主人公の「私」はマリエを救うことをめざしていたけれど、それによってほんとうに救われたのは「私」自身であることは明白です。
そして、まりえの側では、やっぱり本能的に彼女が大人になるためのイニシエーションに取り組んでいたのです。
妹は大人になる前に死んでしまったけれど、まりえは生き抜くための道を探して、いったんそれとは知らずに亡き母の残した洋服の中に潜り込んで、そこからこの世の中に出ていくチャンスを窺う……。
もしかして、それはまりえにとっての「穴」だったのかもしれないけれど、イデア、すわなち騎士団長は自らが死ぬことによってまりえをそこに導いたわけです。
洋服は、ある意味で大人の女性として生きていく形を象徴しているかもしれません。
でも、そこでまりえを護り、かくまったのは洋服というより、おそらくは亡き母の霊のようなものではなかったのではないでしょうか?
それが「シェキナー」なんです。
そして、その亡き母親はと言えば、謎の多い免色さんの人生の中で唯一といってよい「色彩を与えてくれた」女性でした。
物語の最後に、主人公はいちどは失った妻とふたたび人生を送り、その妻の身籠った子の父となることを望みます。
その妻はといえば、「大人になる前に死んでしまった妹」の面影をたたえた存在でした。
つまり、「私」が大人になるために犠牲にしてしまったかもしれない諸々とふたたび関係を取り戻すことが、そこに示唆されています。
★
失礼な言い方をさせていただくと──
『海辺のカフカ』あたりまでは、村上春樹さんは父親に対して駄々をこねているガキでした。
この世の中を形づくっている、強い力(父)のなかに「悪」を見て、それを敵視していたかのようです。
でも、『1Q84』あたりになると、一見強い力に見えた「父」が、けっして絶対的な存在ではないということに気づき、ある意味でその哀れさにも目が向くようになっていきます。
教団を仕切っているかのように見えるリーダーも、じつはリトル・ピープルという、訳のわからない小さな、ごちゃごちゃした連中に蝕まれ、乗っ取られているだけの存在だったのです。
ただし、そこまではまだ、私/あなた、味方/敵、善/悪……みたいな二分法のなかから出てはいなかったように思われます。
それが、『騎士団長殺し』になると、子は「父」を必要とし、あるときは「父」を殺すけれど、やがていずれかは自分も「父」になるかもしれないのです。
そして、自分を助けてくれる「娘」にも、どこかに「父」がいるはずです。
それが「相対的で流動的な関係性」ということです。
だからこそ──
希望をもって生きようとするなら、
自分自身が誰かの希望に関与する必要があるということ。
自分のためだけでなく、誰かのために生きるという
覚悟が必要だということ。
自分の世界を向こう側に押し開くことによって、
別の誰かの世界との接点を見つけること。
──なんです。
というところで、森田健さんが、自分で「自分の場」を作り替えることはできないけれど、他の人の場には関与できるという話とつながってくる……、と思った次第です。
仏教には、因縁生起という考え方があります。
宗派によって少し解釈が分かれるのですが、まぁ、物事というのはいろいろなことが絡み合ってできている──不変の絶対的な「何か」があるわけではなく、「相対的で流動的な関係性」だけがある……、というような考え方です。
『騎士団長殺し』を読んで、どことなくそんなことを思い返しました。
あるいは、同じく仏教の説話なのですが、こんな話を知っていますか?
天国と地獄の違いについて──。
天国でも地獄でも、食べていくのに十分な食事が与えられているんです。
ただし地上界と違うのは、箸がとても長いということ。
どれくらい長いのかは知りませんが、まぁ、たとえば1mくらいとしましょう。
地獄の人たちは、みんなご馳走を前にしながらじっさいには食事をとることができません。
でも、天国の人たちは、みんなが美味しそうに食事をしているんです。
箸は同じでも、地獄の人たちはそれを自分のために使おうとして食事ができないんだけど、天国の人たちはみんなが自分の箸を使ってほかの人の口元に食事を運んであげているから……。

──そんな説話にも通じるような気がします。
【補遺-1】クリフォト(ケリポート):「白いスバル・フォレスターの男」
「白いスバル・フォレスターの男」のことも書いてほしいというリクエストをいただいたので、少し触れておきます。
作品の中にヒントを求めるとするなら、この人物については「二重メタファー」すわなち、「あなたの中にありながら、あなたにとっての正しい思いをつかまえて、次々に貪り食べてしまうもの、そのようにして肥え太っていくもの」ということが書かれています。
まぁ、ある種の「意識の暴走」と言ってよいかもしれません。
メタファー、すなわち「喩え」というのは1回だから有効なんです。
それが「喩えの喩え」になっていっちゃうと、人を不健全な場所に連れていきかねません。
統合失調症の人の言動の断片だけを取り上げると、一見正しいかのように見えるけれど、それが果てしなく連鎖をしていくうちに狂気の世界を膨らませていくように。
★
「二重メタファー」という表現を聞いて、ジョージ・オーウェルの『1984年』を読んだことのある人なら、そこに出てくる「二重思考」という言葉を思い出すことでしょう。
村上さんはかつて『1Q84』というタイトルで作品を書いているわけだし、彼が『1984年』を意識していないはずはありません。
『1984年』のなかで、「二重思考」とは、「相反し合う二つの意見を同時に持ち、それが矛盾し合うのを承知しながら双方ともに信奉すること」と説明されています。
支配者たちが権力を維持するために、すべての人間に強いられている思考法です。
ぼくたちの身近なところからいうと「ホンネとタテマエ」もそうでしょう。
少し前に政治の世界を飛び交った「忖度(そんたく)」もそれと言えるでしょう。
もっと前なら「大本営発表」とか「主催者側の発表」とか「公式見解によれば」みたいのもそうでしょう。
「二重メタファー」はその裏返し、なのかもしれません。
ありえないはずのことを「あり」にしちゃうことで成り立っている世の中が生み出す、歪んだ影のようなもの……。
★
「暴走」というのは「過剰」ということでもあります。
適切さをはみ出してしまった、行き過ぎ。
「過剰」という言葉を使うと、バタイユを知っている人ならば『呪われた部分』のことを思い出すかもしれません。
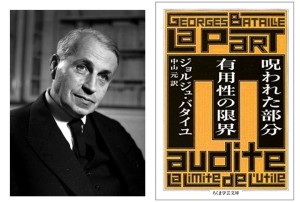
人類は農業を覚えて、本来必要とする以上のものを生産し、蓄えるようになった。
それが「過剰」ということです。
「過剰」なものは必要とする以上のものだから、それを消費する際に、「役に立つ」という束縛から人を解き放ちます。
どんちゃん騒ぎで蕩尽したり、生殖を伴わないエロティシズムに人を誘ったり、芸術や宗教や戦争という人間特有の行動を煽ったり……。
そこには妖しい香りが漂う独特の世界があるけれど、どことなく不健全さを引きずり、しばしば邪悪さが顔をのぞかせることすらあります。
上にあげた諸々とじょうずに付き合うことのできる人は多くはありません。
★
まったく別の、尾籠な喩えを使わせてもらうなら、それは糞便のようなものでもあります。
ものを食べるというのは、基本的に「よきこと」の追求です。
栄養の摂取であったり、美食の楽しみであったり、他者との分かち合いであったり。
でも、「よきこと」を追求した結果、そこをはみ出してしまうものがあります。
それが糞便です。
生きていくために必然的に生み出されたものだけれど、もし放置しておいたなら、甚だ芳しくないものが増殖をしていくことでしょう。
カバラではそれを「クリフォト(ケリポート)」と言ったりします。
それらは「思い浮かべるだけでも、危険で恐ろしい」ものとされるけど、「よきこと」を追求した結果、ときとしてそれらが生まれることは知っておいたほうがいいです。
つまり、家にはトイレが必要だということです。
糞便というのは、いじったり、人前で大声で話題にしたりするものではないけれど、必ず出てくるものだから、きちんと処理ができるようにしておくのです。
★
「白いスバル・フォレスターの男」は、この作品の中でとくに肯定的な役割を果たしているとは言いがたいです。
にもかかわらず、この作品が成り立つためにはその存在が必要──村上さんの芸術的感受性がそのように働いたものと思われます。
でも、それは糞便のようなものだから、「いずれはそれと取り組む必要があるのかもしれないけれど、いまはまだくわしくその姿を明確にさせてはいけない」存在ということなんです。
ちなみに「白いスバル・フォレスターの男」は、主人公の「私」が放浪中、一度かぎり女性と交わるのに伴って出てきた人物。
その女性もある意味でベイバロンであり妹(いも)なんだけど、性交中に首を絞められることを望みます。
まぁ、世の中にはたしかにそのような嗜好もあるんだけど、でも同時にそれは象徴的に彼女を殺すことと見ることもできるでしょう。
そして、この女性との交わりは、後になって明かされる、彼の妻ユズの妊娠についてメタファーを提供してもいます。
カバラでは、神の「光」が「器」に注がれる際、受け止めきれずに器が破壊されると言います。
そこから溢れ出た光がこの世界を形づくり、破壊された器のかけらが「クリフォト(ケリポート)」です。
いささか図式的な解釈をするなら、いちどかぎり交わった女性はベイバロンであり、シェキナーの入口でした。
そこに「私」の精液という光が注がれて、「あたらしい子」が形づくられる。
それに並行して排出される「クリフォト(ケリポート)」が「白いスバル・フォレスターの男」というわけです。
その人物は「私」がまりえと、そして彼自身の人生を救うドラマ──つまり、ある意味で世界を作り直すチャレンジへと向かう際に、チラリとだけその影を垣間見せます。
★
『1Q84』では、もしかしたら天吾の父がその役割を果たしていたかもしれません。
導き手でもなく、乗り越えるべき壁でも、倒すべき敵でもなく、盟友でもなければ、傍観者ですらありません。
天吾の人生の歩みにとって、さらにはストーリーの上においても何ら生産的な役割を果たすことなく、一言でいうなら「困った人」としてそこに居つづける……。
ひたすらNHKの集金をするだけのために生きているかのような人物です。
NHKの集金は「正しいこと」であり、そして天吾を養い育ててくれたのは「よきこと」なんだけど、健全な範疇を超えて嵌まり込んでしまった「クリフォート(ケリポート)」のような存在といってよいでしょう。
芸術作品が成立する際には、しばしばそのような「過剰」が必要とされるんです。
家を建てる際には、トイレを作っておかないといけない。
ことさらに、そこをクローズアップするのは適切ではないけれど、でもやっぱりそれは必要なんです。
★
心理学でいわれる「シャドー(影)」は、これとよく似ていますが根本的に別物です。
「シャドー(影)」は、あくまでも自分の大切な一部であり、どこかで統合することが求められるものです。
でも、「クリフォト(ケリポート)」はちょっと違います。
「糞便」はもはや自分の一部ではないから、統合は不可能なんです。
「トリックスター(道化)」としてなら、いっときの間、つきあうことができるかもしれません。
ちょっとしたお下品なネタにして真面目くさった空気を吹き飛ばしたり、あるいはスカトロジーで羽目をはずしたり……。
あるいは、稀には「犠牲」として、ぼくたちを支えることもあるかもしれません。
たとえば、堆肥として作物を育てることを助けてくれたり……。
でも、そこでも必ず残り滓が出ます。
それが、あらたな「クリフォト(ケリポート)」ということです。
何か「よきこと」が生じるたびに、必ず「クリフォト(ケリポート)」が排出される──その理から逃れることはできないんです。
けっきょくのところ、「よきこと」を望んでいるうちはトイレが必要であり、完全な統合を志すのであれば「よきこと」の向こうに行かないといけないわけです。
「よきこと」の向こう──たとえば、このサイトでいえば<意識のめざめ>がそれにあたったりするわけですが……。
【補遺-2】響き合い
たくさん書いたから、もういいかなと思ってたんだけど、やっぱりあともうひとつ書いておきたいことがあって追記します。
それは「響き合い」ということ。
単純に言えば、この世は人と人の響き合いです。
お互いに影響を与え、影響を受け、あるいはその響き合いをとおして、ハーモニーが生まれたり、不協和音が生まれたり……。
そんなことなら、わざわざ言うまでもなく、誰もが先刻承知のことでしょう。
ところが村上さんは、それを個人の単位だけでなく、ストーリーや小説作品全体にまで拡げようとするのです。
あるストーリーと、別のストーリーの響き合い。
ある小説作品と、別の小説作品の響き合い。
たぶん、村上さんが明確にそれを意識しだしたのは『世界の終わりとハートボイルドワンダーランド』からじゃないかな。
この作品は「世界の終わり」と「ハードボイルドワンダーランド」というふたつの話が一見脈絡なく交互に示され、最後になってそれがつながる。
ぼくには、それがアートとして成功したとは思えなかったけれど、『1Q84』における試みは美しい結晶をもたらすに至ったと思います。
<天吾の世界>と<青豆の世界>、そして天吾と青豆が重なりそうで、(そして重なってほしいという想いをかきたてつつ)、なかなか重ならない、それが最後に……。
★
村上さんは、何度かひとつの作品の中でふたつの物語の響き合いにチャレンジしているけれど、他の人の作品との響き合いも意識しているはずです。
たとえば、『1Q84』はタイトルのみならず、内容的にも明らかにジョージ・オーウェルの『1984年』を前提にしています。
タイトルをいうなら、『ノルウェイの森』もそう。
いわずとしれたビートルズのナンバーが背景にあるけれど、ちなみに重箱の隅をつつくと日本におけるビートルズのタイトルは『ノルウェーの森』。
もともと村上さんは『雨の中の庭』という題名で書き始めたらしいけれど、原稿を版元に渡す2日前に奥さんに相談したら「『ノルウェイの森』でいいんじゃない?」ということで急遽変更されたとか……。
ちなみに、『雨の中の庭』のほうはドビュッシーのピアノ曲に由来するタイトルらしいです。
『雨の中の庭』だったら、あそこまで売れたかどうか^^
ちなみに、ビートルズファンのあいだでは『ノルウェーの森』という邦題は誤訳じゃないかと言われています。
原題は“Norwegian Wood”。森なら‘Woods’のはず。
まぁ、歌詞の最後に唐突に Isn’t it good, Norwegian wood というフレーズが出てきて、‘good’と‘wood’が韻を踏んでいるので、ここはどうしても‘woods’じゃなくて‘wood’なんだけど。
そして、曲全体を聴くと、これは女の子の部屋を訪れた男の子の歌だから、部屋の中に森があるのはヘン。
ちなみに、英語では「ノルウェー産の材木」という言葉には、安アパートの建材というニュアンスがあるんだそうです。
村上さんも当然そのことは知っていて、それで日本にける洋楽タイトルとちょっとだけ変えたのか、あるいは著作権の問題があったか……?
いずれにせよ、タイトルをそうすることで、ビートルズの残り香が漂うあの時代と響き合い、ブルーでやるせない、あの曲の雰囲気と響き合い、青春の勢いで突っ走っていたビートルたちがやがて複雑な屈折を見せはじめたバンドヒストリーと響き合う……。
★
そもそもぼくたちが色々なことを考えたり、感じたりするそのしかたというのは、すべてほかの誰かから学んだものです。
完全に「オリジナル」というものはどこにもありません。
とくに、村上さんのような小説家であれば、そのことを痛感せずにはいられないはずです。
どんな物語も、すでにいつかどこかで語られた別の物語の焼き直しと順列組み合わせでしか作ることはできません。
村上さんが、明確に他の人の作品との響き合いを意識しはじめたのは『海辺のカフカ』あたりからじゃないかな。
まぁ、「カフカ」という名前じたいがフランツ・カフカとの響き合いだし、内容的にもエディプス王の物語から、さらには『源氏物語』や『雨月物語』などからの転用があちこちに見受けられます。
ぼくたちは、他人の物語と響き合って生きているんです。
★
それを言うなら、今回の『騎士団長殺し』は『ドン・ジョバンニ』との響き合いが大前提です。
さらに、今回はとくにご自身の過去の作品との響き合いも意識なさっています。
途中何度か「風の歌」というフレーズが出てくるけれど、これはご自身のデビュー作。
「免色さん」という名前は『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』。
穴とか井戸とか森は村上作品の定番と言ってもいいアイテム。
そのことを、「村上作品を楽しむためのカタログ」と評した論者もいるけれど、ぼくはその視点にはビミョーな悪意と理解のズレを感じます。
いまの自分は、過去の自分と響き合っている。
響き合っているけれど、同じではない。
響き合いの中から、あたらしい別の何かが生まれてくる……。
書いている村上さんもきっとそうだったと思うけれど、読んでいるぼくもそれぞれの時代に村上作品を読んできた、過去の読書体験と、その時代と、そのときの自分と響き合いながら今回のあたらしい作品体験を深めていく……。
★
少し前、ポストモダン全盛期には引用だとか、意図的な剽窃だとか、表面的な形式で遊ぶことだとか、音楽でいうとサンプリングなどがずいぶんと流行ったものです。
それはそれで面白かったけれど、他の人や、他の作品に対する愛やリスペクトは薄かったように思います。
軽やかさや戯れは、生きることを雑に扱うこととは違います。
村上さんはポストモダンに染まることはなかったけれど、でもその遺産のもっとも重要な要素をしっかりとご自分のものにされていらっしゃいます。
★
ぼくのこの独りよがりの文章も、村上さんとそしてもちろんぼくがこれまで触れてきたたくさんの人たちとの響き合いで書いているものだし、読者の数は村上さんの1万分の1にも満たないけれど、いまこれを読んでくれている「あなた」とも響き合えたら素敵だなと思います。